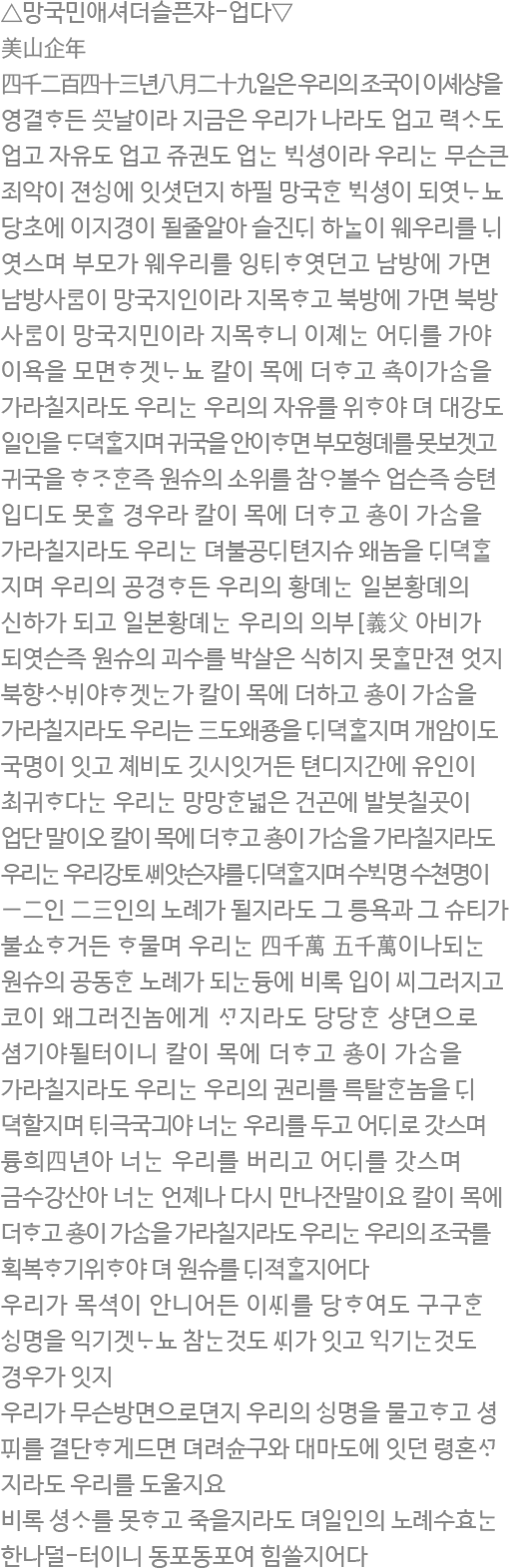10. 哀莫哀於亡国民、「新韓民報」
(1910年9月21日)
哀莫哀於亡国民
亡国民ほど悲しい者はない
美山企年
4243年(訳注_1910年)8月29日は、我々の祖国がこの世と永訣した最期の日だ。今、我々は国もなく、歴史もなく、自由もなく、主権もない百姓である。我々が前世にいかに大きな罪悪を犯して、惜しくも亡国の民となったのか。初めからこんな境遇に陥ると知っていたならば、天はなぜ我々を生み、親はなぜ我々を身ごもったのか。南方に行けば南方の人々が亡国の民と指差し、北方に行けば北方の人々が亡国の民と指差す。一体どこに行けば、そのような恥から逃れるられるのか。首に刀を突きつけられ、銃を胸に当てられても、我々は我々の自由のためにあの大強盗の日人と戦うのだ。 帰国しなければ親兄弟に会えない、帰国したら敵の振る舞いを黙って見てはいられない。死んでも土に還ることなんてできはしない。
首に刀を突きつけられ、銃を胸に当てられても、我々は決して許すことのできない 不倶戴天の敵である倭奴と戦う。我々の尊敬する我々の皇帝は日本の皇帝の臣下となり、日本の皇帝は我々の義父になった。つまり、敵の首魁を殺すことはできなくとも、どうやって拝礼を行うことができるだろうか。首に刀を突きつけられ、銃を胸に当てられても、我々は倭種と戦う。ハシバミの木にも穴があり、燕にも巣があるというのに、この世で人間が最も貴い存在であるはずなのに、我々は茫々たるこの天と地において休める居場所がない。
首に刀を突きつけられ、銃を胸に当てられても、我々は我々の領土を奪った者と戦う。数百人、数千人が一、二人あるいは二、三人の奴隷になっても、その陵辱と不名誉の程度が甚だしいといえるのに、ましてや我々は4千万、5千万にも及ぶ敵の共同の奴隷となる。たとえ口が裂け、鼻が曲がった奴にさえ、主人として仕えなければならないのだ。首に刀を突きつけられ、銃口を胸に当てられても、我々は我々の権利を奪った輩と戦う。
太極国旗よ、お前は我々を置いて、どこへ行ってしまったのか。隆熙4年(訳注_1910年)よ、お前は我々を捨てて、どこへ 行ってしまったのだ。錦繡江山よ、いつまたお前に会えるというのか。首に刀を突きつけられ、銃を胸に当てられても、我々は我々の祖国を取り戻すために、あの敵と戦う。我々は木石ではない。この期に及んでつまらない命なぞ惜しくない。我慢にも限界がある。惜しんでいる場合ではない。我々がいかなる方策であろうと、我々の命を惜しまず、覚悟を決めたら、旅順口と対馬島にある魂までもが我々を手助けするだろう。たとえ失敗して死ぬことになっても、日人の奴隷の数は一人減るのだから、同胞たちよ、頑張るのだ。