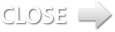明治時代、日本の内務省は鬱陵島と独島を島根県の地籍に入れるべきかについて「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」を当時の最高行政機関である太政官に提出しました。
これに対して1877年3月、太政官は元禄年間の朝鮮朝廷と江戸幕府間交渉(鬱陵島争界=竹島一件)の結果、独島が日本に付属しないことが確認されたと判断、「竹島(鬱陵島)外一島(独島)の件は、本邦(日本)とは関係ないとのことを心得るべし」という指示を内務省に下しました。これを「太政官指令」といいます。
「太政官指令」 / 「磯竹島略図」
- 明治10年3月20日
- 別紙にて内務省が伺った「日本海内竹島外一島地籍編纂の件」については、元禄5年朝鮮人が入島して以来、旧政府(江戸幕府)と朝鮮国間で交渉が行われた結果、結局本邦(日本)とは関係ないことが確認されたようだと申し立てきた以上は、伺の趣旨を踏まえて次の通り指令を下しても宜しいでしょうか、このことをお伺いいたします。
- ご指令按
- お伺いの件、竹島(鬱陵島)ほか一島(独島)については本邦(日本)とは関係ないということを心得るべきこと
原文
- 明治十年三月廿日
- 別紙内務省伺日本海内竹嶋外一嶋地籍編纂之件
- 右ハ元禄五年朝鮮人入嶋以来旧政府該国ト往復之末遂ニ本邦関係無之相聞候段申立候上ハ伺之趣御聞置左之通御指令相成可然哉此段相伺候也
- 御指令按
- 伺之趣竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事
上記の伺いに添付された「磯竹島略図」に竹島(鬱陵島)と松島(独島)が描かれていることなどから、「太政官指令」で言う"竹島(鬱陵島)他一島"の"一島"が独島であることは明らかです。
「太政官指令」を通じて、日本政府が17世紀の朝日両国間における鬱陵島争界(竹島一件)の交渉過程で鬱陵島と独島の所属が確認されたことを認識していたことがよく分かります。
また、「太政官指令」が出される数年前である1870年に外務省の佐田白茅らが朝鮮視察後に外務省に提出した報告書(『朝鮮国交際始末内探書』)にも、“竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮付属になった始末”が書かれており、当時日本の外務省がこの二つの島を朝鮮領として認識していた事実がうかがえます。